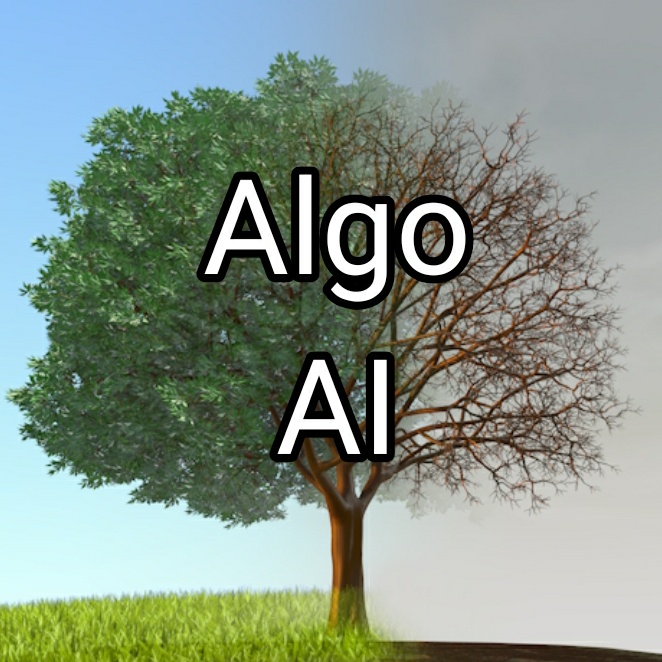JICAの災害支援:緊急援助から復興、そして「より良い復興(Build Back Better)」へ
近年、世界中で自然災害の増加が深刻化しており、その影響は甚大です。気候変動による異常気象や、人口増加による都市化の進展などが原因と考えられています。2020年の世界災害報告では、過去10年間で自然災害による経済損失は2兆ドルを超え、毎年、世界で平均1億人が災害の影響を受けていると推定されています。日本でも、近年、台風や豪雨による被害が相次いでおり、深刻な状況が続いています。
このような状況の中で、国際協力機関であるJICAは、災害支援において重要な役割を果たしています。JICAは、災害発生時の緊急援助から、復旧・復興支援、そして将来の災害に備えるための防災の事前投資まで、幅広い支援を行っています。本記事では、JICAの災害支援の3つの段階と、「より良い復興(Build Back Better)」の概念を詳しく解説します。
JICAの災害支援の3つの段階
JICAの災害支援は、大きく分けて3つの段階で行われています。
1. 応急対応段階
災害発生直後には、人命救助や負傷者の治療、食料や水などの生活必需品の供給が最優先となります。JICAは、国際緊急援助隊(JDR)を派遣し、被災地の状況を把握し、必要な支援を迅速に行います。
JDRは、医療チーム、専門家チーム、捜索救助隊など、さまざまな専門分野の隊員から構成され、災害発生後、いち早く被災地に入り、人命救助、負傷者の治療、避難所の運営、緊急物資の供給などの活動を行います。
具体的には、東日本大震災では、JDRは、被災地への緊急物資輸送、医療支援、瓦礫撤去、避難所の運営などの活動を展開しました。また、ネパール地震では、緊急物資の輸送と医療チームの派遣を実施し、フィリピン台風被害では、医療チームと専門家チームを派遣し、被災者の治療や復興支援を行いました。
2. 復旧・復興段階
災害発生から数か月後から数年間にわたって、被災地のインフラや経済活動を復興させるための支援が行われます。JICAは、被災地の状況を把握し、住民のニーズに合わせた支援を行います。
2013年11月8日に発生した台風ヨランダは、フィリピンを直撃し、大きな被害をもたらしました。JICAは、被災地の復興を支援するため、住居復興支援、インフラ整備、経済活性化支援、教育・医療分野の支援など、多岐にわたる支援を行いました。
例えば、住居復興支援では、仮設住宅の建設や住宅の改修、家財道具の供与などを実施しました。また、インフラ整備では、道路や橋などの公共施設の修復や、新しいインフラの建設を行いました。さらに、経済活性化支援では、中小企業の支援、農業や漁業の復興支援、雇用創出などを実施しました。
3. 抑止・減災(防災の事前投資)段階
災害の被害を最小限に抑えるためには、事前に防災対策を行うことが重要です。JICAは、将来の災害に備え、被災地の防災能力強化を支援しています。
JICAは、仙台防災枠組2015-2030に基づき、ハザードマップ作成、土地利用計画の改訂、防災教育の推進など、さまざまな防災対策を支援しています。
具体的には、地震対策では、耐震性のある建築物の建設や、地震発生時の安全確保のための訓練などを支援しています。また、津波対策では、防潮堤の建設や、津波発生時の避難経路の確保などを支援しています。さらに、洪水対策では、河川の改修や、洪水時の排水対策などを支援しています。
JICAの防災支援がもたらす効果
JICAの災害支援は、被災地の復興を促進し、より災害に強い社会の構築に貢献しています。JICAの災害支援によって、次のような効果が期待できます。
- 住民生活の改善: 住居、インフラ、経済活動などが回復し、住民の生活水準が向上します。
- 経済活動の回復: 被災地の産業が復興し、経済活動が活発化します。
- 防災意識の向上: 防災教育や訓練を通して、住民の防災意識が高まり、災害への備えが向上します。
- コミュニティの強化: 住民が協力して復興に取り組むことで、地域コミュニティが強化されます。
JICAは、「Build Back Better」の概念に基づき、災害に強い社会の構築を目指しています。「Build Back Better」とは、災害発生を契機として、物理的なインフラの復旧だけでなく、生活水準、経済、産業の復興、そして地域の環境と文化の復旧を通じて、より強靭な国家と社会を造るという概念です。
具体的には、耐震性のあるインフラ整備、早期警戒システムの導入、防災教育の推進など、さまざまな取り組みを通して、災害に強い社会の構築を目指しています。
日本の防災技術やノウハウが世界でどのように活用されているか
日本は、地震や津波などの自然災害が多い国であり、長年の経験を通して、独自の防災技術やノウハウを蓄積してきました。
JICAは、日本の防災技術やノウハウを世界に広め、途上国の防災能力強化を支援しています。
具体的には、耐震建築技術、津波対策技術、早期警戒システム、防災教育プログラムなど、さまざまな技術やノウハウを、JICAの技術協力を通して、世界各国で共有しています。
例えば、JICAは、インドネシアで耐震性のある学校の建設を支援し、フィリピンでは、津波発生時の早期警戒システムの導入を支援しました。また、世界各国で防災教育プログラムの導入を支援し、住民の防災意識向上に貢献しています。
今後の展望
JICAは、今後も、災害支援の3つの段階を継続的に実施していくとともに、気候変動への対応、都市部における防災対策、人材育成、技術革新など、新たな課題に対応していく予定です。
特に、気候変動の影響が深刻化する中で、気候変動に適応した防災対策の重要性が高まっています。JICAは、気候変動への対応を強化し、より効果的な防災支援を展開していく予定です。
また、都市部における防災対策も重要です。都市部では、人口密度が高く、災害発生時の被害が大きくなる可能性があります。JICAは、都市部の防災対策を支援し、災害に強い都市づくりを目指していきます。
さらに、防災分野における人材育成も重要です。JICAは、途上国の防災専門家育成を支援し、将来の災害に備えるための体制強化を支援していく予定です。
JICAは、これからも、世界の人々と協力し、災害に強い持続可能な社会の実現に向けて、積極的に取り組んでいきます。
読者の皆様も、防災への意識を高め、国際協力への参加をご検討ください。