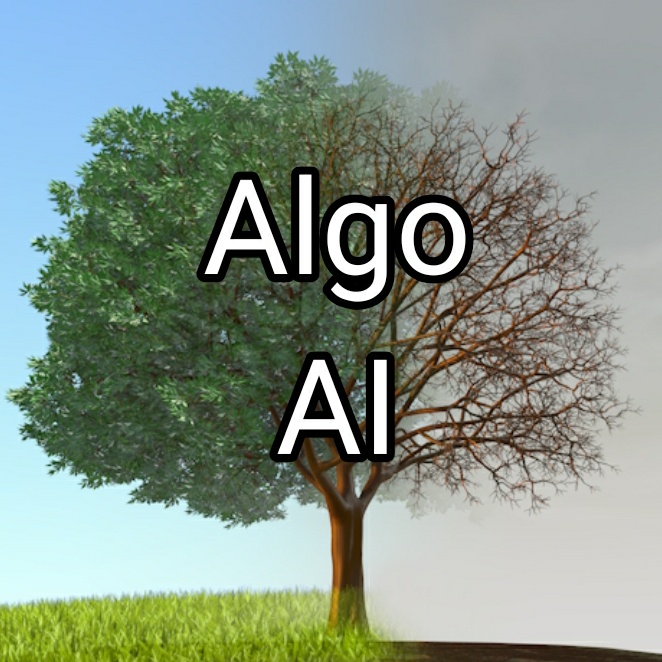地震のスーパーサイクル
地震は、地球上で最も破壊的な自然災害の一つです。地震の発生は、地殻の断層運動によって引き起こされ、その頻度と強さは、断層の種類や規模、そして地震サイクルと呼ばれる一連のイベントによって影響を受けます。従来、地震サイクルは、ポアソンモデルと地震サイクルモデルの二つによって説明されてきました。
- ポアソンモデルは、地震発生が確率的に独立しており、過去に地震が発生したかどうかは将来の地震発生確率に影響を与えないと仮定しています。
- 地震サイクルモデルは、地震発生が、断層の歪み蓄積と解放によって周期的に起こると仮定しています。地震によって蓄積された歪みが解放され、その後の地震発生までに再び歪みが蓄積され、これが繰り返し起こるとされています。
しかし、地震サイクルの研究が進められるにつれて、これらのモデルでは説明できない、より長期間にわたる地震活動のパターンが明らかになってきました。このようなパターンは、スーパーサイクルと呼ばれています。
目次
スーパーサイクルの定義
スーパーサイクルは、従来の地震サイクルモデルでは説明できない、長期間にわたる地震活動のパターンです。具体的には、複数回の地震サイクルを跨いでの地震活動の周期性や、地震発生の集中と空白期間の繰り返しを特徴としています。
スーパーサイクルの重要性
スーパーサイクルの理解は、地震発生の予測とハザード評価において非常に重要です。従来のモデルでは、地震発生確率は時間経過とともに一定とされ、または前回の地震からの経過時間のみを考慮していました。しかし、スーパーサイクルを考慮すると、地震発生確率は、前回の地震からの経過時間だけでなく、過去の地震活動の履歴や断層の長期的な歪み蓄積量も考慮する必要があります。
スーパーサイクルの例
スーパーサイクルは、世界中のさまざまな断層で観測されています。その例として、以下のようなものがあります。
サンアンドレアス断層
サンアンドレアス断層は、北アメリカプレートと太平洋プレートの境界に位置し、カリフォルニア州を南北に貫く活断層です。この断層では、スーパーサイクルの証拠が見つかっています。
- 長期的な歪み蓄積と解放: 地質学的な調査によって、サンアンドレアス断層では、数千年にわたって断層の歪みが蓄積されてきたことが明らかになっています。そして、大きな地震が発生すると、蓄積された歪みが解放され、その後再び歪みが蓄積されるプロセスが繰り返されます。
- 地震活動の集中と空白期間: サンアンドレアス断層では、地震活動が、数百年程度の集中した活動期間と、それよりも長い空白期間を繰り返していることが観測されています。これらのパターンは、スーパーサイクルの存在を示唆しています。
スマトラ海溝
スマトラ海溝は、インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートの下に沈み込む、インド洋の巨大な海溝です。2004年に発生したスマトラ沖地震は、マグニチュード9.1という巨大地震であり、津波を引き起こし、世界中に大きな被害をもたらしました。
- 巨大地震の発生とスーパーサイクル: スマトラ海溝では、2004年の巨大地震以外にも、過去にも複数回の巨大地震が発生していることが知られています。これらの巨大地震の発生間隔は約200年程度と推定されており、この間隔は、地震サイクルモデルで説明できる範囲を超えています。
- 地震活動の履歴: 地質学的な調査によって、スマトラ海溝では、巨大地震が、数百年程度の集中した活動期間と、それよりも長い空白期間を繰り返していることが明らかになっています。これらのパターンは、スーパーサイクルの存在を示唆しています。
カスケード海溝
カスケード海溝は、北アメリカプレートと太平洋プレートの境界に位置し、アメリカ合衆国北西部とカナダのブリティッシュコロンビア州に沿って延びる海溝です。この海溝では、スーパーサイクルと津波のリスクが関連付けられています。
- スーパーサイクルと津波のリスク: カスケード海溝では、過去の巨大地震によって、巨大な津波が発生したことが知られています。地質学的な調査によって、カスケード海溝では、巨大地震と津波が、数百年の周期で発生していることが明らかになっています。
- 地震発生確率の推定: これらの調査結果から、カスケード海溝では、今後数百年以内に巨大地震と津波が発生する可能性が高いと推定されています。
日本海溝
日本海溝は、太平洋プレートが北アメリカプレート(オホーツクプレート)の下に沈み込む、日本列島東岸に沿って延びる海溝です。2011年に発生した東日本大震災は、日本海溝で発生したマグニチュード9.0という巨大地震であり、津波を引き起こし、日本に大きな被害をもたらしました。
- 東日本大震災の観点から: 東日本大震災は、過去の巨大地震に比べて、発生間隔が短く、そして震源域が広く、地震規模が大きかったことが特徴です。これらの特徴は、日本海溝でスーパーサイクルが働いている可能性を示唆しています。
- 地震活動の集中: 地質学的な調査によって、日本海溝では、巨大地震が、数百年程度の集中した活動期間と、それよりも長い空白期間を繰り返していることが明らかになっています。これらのパターンは、スーパーサイクルの存在を示唆しています。
死海変換断層
死海変換断層は、アラビアプレートとアフリカプレートの境界に位置し、中東を横断する活断層です。この断層では、スーパーサイクルと断層の変形が関連付けられています。
- スーパーサイクルと断層の変形: 死海変換断層では、過去の巨大地震によって、断層の変形や地表の隆起・沈降が発生したことが知られています。地質学的な調査によって、死海変換断層では、これらのイベントが、数百年程度の周期で発生していることが明らかになっています。
- 地震活動の履歴: 地質学的な調査によって、死海変換断層では、地震活動が、数百年程度の集中した活動期間と、それよりも長い空白期間を繰り返していることが明らかになっています。これらのパターンは、スーパーサイクルの存在を示唆しています。
オーストラリア大陸内部の断層
オーストラリア大陸内部の断層は、プレート境界とは異なる場所で発生する地震の例です。この地域では、スーパーサイクルと断層の長期的な変形との関係が指摘されています。
- 陸地におけるスーパーサイクル: オーストラリア大陸内部の断層では、過去の地震によって、断層の変形や地表の隆起・沈降が発生したことが知られています。地質学的な調査によって、これらのイベントが、数万年から数十万年の周期で発生していることが明らかになっています。
- 地震活動の履歴: 地質学的な調査によって、オーストラリア大陸内部の断層では、地震活動が、数万年から数十万年の集中した活動期間と、それよりも長い空白期間を繰り返していることが明らかになっています。これらのパターンは、スーパーサイクルの存在を示唆しています。
スーパーサイクルのモデル化
スーパーサイクルを説明するために、従来のモデルでは説明できなかった長期的な断層の記憶(Long-Term Fault Memory:LTFM)を考慮したモデルが提案されています。
従来のモデルの限界
ポアソンモデルと地震サイクルモデルは、地震発生を確率的な現象として捉えていますが、スーパーサイクルのような長期間にわたる地震活動の集中と空白期間の繰り返しを説明することはできません。これらのモデルは、断層が過去の地震活動の履歴を記憶しておらず、前回の地震からの経過時間のみを考慮して、次の地震発生確率を決定すると仮定しています。しかし、スーパーサイクルの存在は、断層が過去の地震活動の履歴を記憶し、その影響が複数回の地震サイクルにわたって続くことを示唆しています。
長期断層記憶(LTFM)モデル
長期断層記憶(LTFM)モデルは、断層が過去の地震活動の履歴を記憶し、その記憶が、次の地震発生確率に影響を与えると仮定したモデルです。LTFMモデルでは、地震発生確率は、前回の地震からの経過時間だけでなく、過去の地震活動の履歴や断層の長期的な歪み蓄積量も考慮されます。
- 歪み蓄積と解放: LTFMモデルでは、断層は、過去の地震によって解放された歪みだけでなく、過去の地震活動の履歴も記憶しています。そのため、次の地震発生確率は、前回の地震からの経過時間だけでなく、過去の地震活動の履歴も考慮されます。
- 地震発生確率の変化: LTFMモデルでは、断層の歪み蓄積量が増加するにつれて、地震発生確率も上昇します。地震が発生すると、歪みが解放され、地震発生確率は低下しますが、必ずしもゼロにはなりません。そのため、地震発生確率は、前回の地震からの経過時間だけでなく、過去の地震活動の履歴も反映します。
LTFMモデルのシミュレーション
LTFMモデルを用いたシミュレーションでは、スーパーサイクルの期間、地震発生間隔の分布、地震のクラスターなどが再現されます。
スーパーサイクルの期間
LTFMモデルのシミュレーションでは、スーパーサイクルの期間は、断層の特性、歪み蓄積速度、そして地震発生による歪み解放量によって変化します。一般的に、歪み蓄積速度が遅い場合、スーパーサイクルの期間は長くなります。また、地震発生による歪み解放量が大きい場合、スーパーサイクルの期間は短くなります。
地震発生間隔の分布
LTFMモデルのシミュレーション結果では、地震発生間隔の分布は、周期性、弱周期性、バースト性などが再現されます。
- 周期性: スーパーサイクルが明瞭な場合、地震発生間隔は周期的に分布します。
- 弱周期性: スーパーサイクルが明瞭ではない場合、地震発生間隔は弱周期的に分布します。
- バースト性: 地震活動が集中する期間(バースト)と、活動が沈静化する期間(空白期間)が交互に繰り返される場合、地震発生間隔はバースト的に分布します。
地震のクラスター
LTFMモデルのシミュレーションでは、地震活動の集中(クラスター)が再現されます。これは、地震発生による歪み解放量が小さい場合、または地震発生間隔が短い場合に起こりやすく、過去の地震活動の履歴が、次の地震発生確率に影響を与えるためです。
スーパーサイクルが地震ハザード評価に与える影響
スーパーサイクルは、地震ハザード評価に大きな影響を与えます。
地震発生確率の推定
LTFMモデルを用いることで、従来のモデルよりも、より正確な地震発生確率の推定が可能になります。LTFMモデルでは、過去の地震活動の履歴や断層の長期的な歪み蓄積量も考慮されるため、従来のモデルよりも、将来の地震発生確率をより正確に推定することができます。
スーパーサイクルによるハザード評価の変動
スーパーサイクルを考慮することで、地震ハザード評価は、従来の評価方法と比べて大きく変わる可能性があります。例えば、ある断層が、スーパーサイクルの活動期間にあると判断した場合、従来の評価方法では、地震発生確率は低く見積もられる可能性があります。一方で、スーパーサイクルの空白期間にあると判断した場合、従来の評価方法では、地震発生確率は高く見積もられる可能性があります。
今後の展望
スーパーサイクルに関する研究は、まだ発展途上です。今後の研究では、以下のような課題に取り組む必要があります。
- 3次元モデル開発: 現在のLTFMモデルは、2次元モデルが中心ですが、より現実的な地震活動を再現するためには、3次元モデルの開発が必要です。
- 断層相互作用の考慮: スーパーサイクルは、複数の断層の相互作用によって生じることがあります。そのため、断層相互作用を考慮したモデルの開発が必要です。
- 温度依存摩擦の考慮: 断層の摩擦力は、温度によって影響を受けます。そのため、温度依存摩擦を考慮したモデルの開発が必要です。
まとめ
地震のスーパーサイクルは、地震リスク軽減のための重要な研究分野となっています。スーパーサイクルを理解することで、より正確な地震発生確率の推定や、地震ハザード評価の精度向上に貢献することが期待されます。今後の研究の進展によって、地震に対する備えを強化することが期待されます。