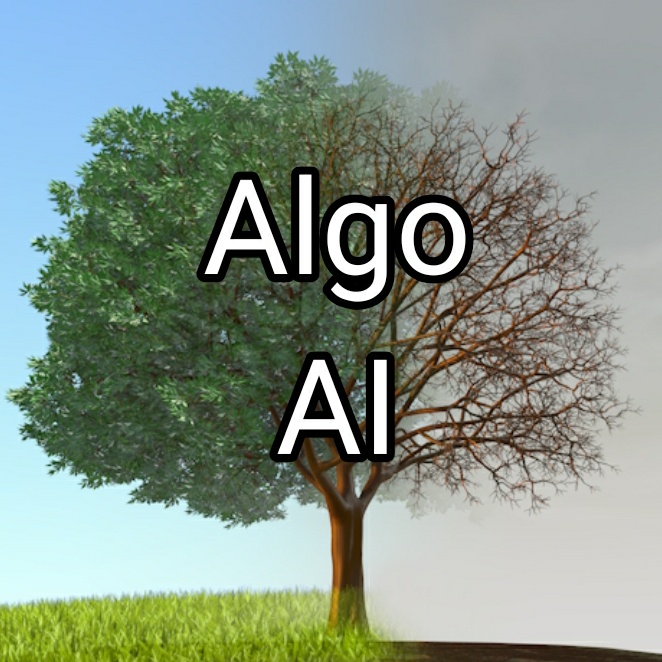日本海溝における地震活動のスーパーサイクル:摩擦と構造の両方の影響
2011年の東北地方太平洋沖地震は、日本海溝で発生した巨大地震であり、その後の地震活動にも大きな影響を与えました。この地震は、プレート境界の摩擦と構造の複雑な相互作用によって発生したと考えられています。本ブログでは、2次元流体力学モデルを用いて、地震活動のスーパーサイクルと、その発生メカニズムについて解説します。
はじめに
日本海溝は、太平洋プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む場所です。この沈み込み帯では、地震や津波が発生しやすいことが知られています。2011年の東北地方太平洋沖地震は、この日本海溝で発生した巨大地震であり、その後の地震活動にも大きな影響を与えました。この地震は、プレート境界の摩擦と構造の複雑な相互作用によって発生したと考えられています。
スーパーサイクルとは、巨大地震が繰り返し発生する周期的なパターンを指します。 巨大地震が発生すると、プレート境界に蓄積されていた歪みが解消され、その後、再び歪みが蓄積されていきます。この歪みの蓄積と解消を繰り返すことで、スーパーサイクルが生じます。
スーパーサイクルの理解は、地震予知にとって非常に重要です。地震予知は、現在まだ実現していませんが、スーパーサイクルのメカニズムを解明することで、将来発生する巨大地震の時期や規模を予測できる可能性があります。
2次元流体力学モデルによるスーパーサイクルの解明
本研究では、スーパーサイクルのメカニズムを解明するために、2次元流体力学モデルを用いました。このモデルは、日本海溝の断面図に基づいており、海溝、前弧、火山弧、マントルウェッジなどの構造境界を考慮しています。
モデルの重要な特徴は以下の通りです。
- 摩擦係数と粘性率の違い: 各構造境界における摩擦係数と粘性率は異なっています。例えば、海溝付近では、堆積物が多く、摩擦係数は低くなっています。一方、マントルウェッジでは、岩石が固く、摩擦係数は高くなっています。
- 速度依存摩擦則: このモデルでは、速度依存摩擦則が用いられています。この摩擦則では、摩擦係数は滑り速度に依存します。滑り速度が速くなると、摩擦係数は低くなり、滑りが不安定になります。
シミュレーションの結果
このモデルを用いて、地震活動のシミュレーションを行った結果、スーパーサイクルが発生することが確認されました。
シミュレーション結果の主なポイントは以下の通りです。
- スーパーサイクルの周期: スーパーサイクルの周期は、モデルのパラメータによって異なりますが、約1000年程度でした。
- 大地震・中小地震の発生頻度: スーパーサイクルの間、大地震と中小地震が不規則に発生します。巨大地震の発生直後には、中小地震の発生頻度が高くなり、時間が経つにつれて発生頻度が低下する傾向が見られました。
- 前震・余震の発生メカニズム: モデルでは、巨大地震の前震と余震が発生することが確認されました。前震は、巨大地震の断層破壊が開始する前に、歪みが集中した場所で発生します。余震は、巨大地震の断層破壊後に、周辺の場所で発生します。
- スロー地震・アセismic slipの発生メカニズム: モデルでは、スロー地震とアセismic slipが発生することが確認されました。スロー地震は、断層がゆっくりと滑る現象であり、通常の地震よりもエネルギーが小さいため、震度は小さくても、長時間にわたって観測されます。アセismic slipは、断層がまったく滑らない現象です。
考察
この研究の結果は、日本海溝における地震活動が、摩擦と構造の両方に支配されていることを示唆しています。スーパーサイクルは、プレート境界の歪みの蓄積と解消を繰り返すことで発生します。また、巨大地震の前震や余震、スロー地震やアセismic slipなどの地震活動も、このモデルで再現することができます。
この研究は、地震予知のための重要な知見を提供します。 将来発生する巨大地震の時期や規模を予測するためには、スーパーサイクルのメカニズムをさらに詳しく調べる必要があります。
まとめ
本ブログでは、日本海溝における地震活動のスーパーサイクルと、その発生メカニズムについて解説しました。この研究では、2次元流体力学モデルを用いて、地震活動の複雑さを再現し、摩擦と構造の両方が地震活動に影響を与えていることを示しました。
スーパーサイクルの理解は、地震予知にとって非常に重要です。 将来的には、3次元モデルを用いたシミュレーションや、より詳細な地質学的・地球物理学的観測データを用いることで、より精度の高い地震予測が可能になるかもしれません。